




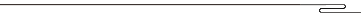
村上春樹文学に関する研究は近年においても依然として盛んだが、これまで「記忆」という視点からの研究はあまり多くない。本書の問題意識に関連する先行研究は、主に以下の四系
 に分けられる。
に分けられる。
 史に注目する作品論
史に注目する作品論
村上春樹文学についての論述は膨大な数に及んでいるので、本書の視座と関連する代表的な論述をここでまとめる。
橋本牧子は、1990年代における〈歴史〉を巡る議論を踏まえ、テクストにおける「満州」という出来事が日本という共同体のトラウマの記忆であり、その暴力によるトラウマから回復するために、登場人物による語りと聴取の行為により〈歴史物語〉の「再構成」が行われたと論じている。
 また、橋本牧子は博士論文『村上春樹論——80年代·90年代の軌迹——』
また、橋本牧子は博士論文『村上春樹論——80年代·90年代の軌迹——』
 の第二部「村上春樹の90年代——〈歴史〉をめぐる物語」で、1990年代に「自由主義史観」などによる侵略否定論が台頭するという言説の空間を視野に入れながら、『ねじまき鳥クロニクル』での「歴史叙述」は「他者の物語に耳を澄ませ、多元的な位相において無数の物語群を「物語る」と肯定的に論じている。本書は橋本牧子の論述を踏まえて、村上による「歴史叙述」、さらにフィクションとしての「記忆」の意味に注目する。
の第二部「村上春樹の90年代——〈歴史〉をめぐる物語」で、1990年代に「自由主義史観」などによる侵略否定論が台頭するという言説の空間を視野に入れながら、『ねじまき鳥クロニクル』での「歴史叙述」は「他者の物語に耳を澄ませ、多元的な位相において無数の物語群を「物語る」と肯定的に論じている。本書は橋本牧子の論述を踏まえて、村上による「歴史叙述」、さらにフィクションとしての「記忆」の意味に注目する。
藤井省三は『村上春樹のなかの中国』で、主に中国語圏における村上春樹文学の翻
 の現状、村上春樹の作品と中国の関わり、魯迅文学と村上文学の相互関係などを論じている。また、短编「トニー滝谷」に注目し、初出版=ショート·バージョン、『レキシントンの幽霊』(文藝春秋、1996年)に収録されたロング·バージョン、全作品版、各版の違いを検討し、さらには『ねじまき鳥クロニクル』との関係を論じている。そして、村上春樹インタビューを引用しつつ、『羊をめぐる冒険』、『ねじまき鳥クロニクル』、『アフターダーク』にみえる歴史の記忆について、「歴史の記忆の影とは、父の战争体験を继承することにより村上の内面でも形成されたある種のトラウマと言っても過言ではあるまい」
の現状、村上春樹の作品と中国の関わり、魯迅文学と村上文学の相互関係などを論じている。また、短编「トニー滝谷」に注目し、初出版=ショート·バージョン、『レキシントンの幽霊』(文藝春秋、1996年)に収録されたロング·バージョン、全作品版、各版の違いを検討し、さらには『ねじまき鳥クロニクル』との関係を論じている。そして、村上春樹インタビューを引用しつつ、『羊をめぐる冒険』、『ねじまき鳥クロニクル』、『アフターダーク』にみえる歴史の記忆について、「歴史の記忆の影とは、父の战争体験を继承することにより村上の内面でも形成されたある種のトラウマと言っても過言ではあるまい」
 と指摘している。
と指摘している。
川村湊はポストコロニアリズム研究の立場で、「羊博士や右翼の大物が行った中国東北部、すなわち“満州”が、当時の日本人にとって〈新天地〉であり、〈新世界〉であったことは言うまでもないだろう」、「その土地の広大さは、まさに“王道楽土”としてあったのだ」、「すでに失われてしまった〈新世界〉——私たちにとって北海道という開拓地や“満州国”という植民地がそうしたものであることは、たぶん膨れあがり、死にそうになった太陽であり、ダダっぴろく、意味のない広がっている心中の砂漠なのである」
[3]
と論じている。また、『ねじまき鳥クロニクル』について、史料調査に基づき、作中の「皮剥ぎ」と「動物への銃殺」という二つの物語の役割や意味を推論し、動物園の銃殺について、「“薬殺”が正しく、猛獣たちを銃殺したという村上春樹の小説の設定はフィクションである」と論じ、ハルハ河は「こちら側」と「あちら側」の境界
 である、としてその象徴的な意味を論じている。
である、としてその象徴的な意味を論じている。
 本書では、川村湊の文献調査に基づく研究を参照しつつも、ノモンハンのエピソードの原型としては、川村が挙げた日露战争時の美談ではなく、村上が挙げた参考文献や中国資料に記録されている、ノモンハン战争直前の出来事や人物を重要な参照対象として提示する。また、「新京動植物園」については、川村が「未見」とした資料も調査し、確認した。
本書では、川村湊の文献調査に基づく研究を参照しつつも、ノモンハンのエピソードの原型としては、川村が挙げた日露战争時の美談ではなく、村上が挙げた参考文献や中国資料に記録されている、ノモンハン战争直前の出来事や人物を重要な参照対象として提示する。また、「新京動植物園」については、川村が「未見」とした資料も調査し、確認した。
柴田勝二は『ねじまき鳥クロニクル』と『アフターダーク』という二つ作品での暴力性に注目し、『ねじまき鳥クロニクル』における歴史叙述について、「歴史叙述自体が客観的な「出来事」の描出によって成り立つのではなく、歴史家という個的な叙述者を主体として、そこに担われた文化的文脈を偏差として含む形でしかなされない側面を持っている。(中略)『ねじまき鳥クロニクル』において、個人の暴力と国家の暴力が時空を超えて響き合う形で配され、また歴史的な事象がつねに個人をめぐる挿話として語られているのは、村上のこうした歴史認識の表現にほかならない」
 と指摘している。
と指摘している。
小森陽一は、『海辺のカフカ』について、ジェンダー、歴史認識の空虚さ等などから、この小説の伝達するイメージの危険さを批判している。「〈精神のある人間として呼吸する女たち〉が記忆していることなど、忘れてもかまわないという許しと、歴史認識が空虚であってもかまわないという許しをすべての
 者に与えること、それが『海辺のカフカ』が〈愈し〉を与える最大の理由なのです」と酷評している。
[4]
者に与えること、それが『海辺のカフカ』が〈愈し〉を与える最大の理由なのです」と酷評している。
[4]
『海辺のカフカ』は本論の中心的な研究対象ではないが、『ねじまき鳥クロニクル』、『1Q84』などの作品における战争や植民地の記忆を考察する際、小森陽一による批評を視野に入れながら、記忆研究という独自な視点で論じることを試み、村上文学における「記忆」のポジティブな意味、及びその限界性を探究する。本書での記忆研究という視点による村上文学の解釈は、作品内外の异なる
 態の「記忆」を取り上げ、「文化的記忆」の現場に接近するのは特徴的である。そして、中国と関わる战争や植民地の記忆を描いた作品を作品群として取り扱い、全体的に論考するのは实践的だと考える。
態の「記忆」を取り上げ、「文化的記忆」の現場に接近するのは特徴的である。そして、中国と関わる战争や植民地の記忆を描いた作品を作品群として取り扱い、全体的に論考するのは实践的だと考える。
本論は、村上文学における「記忆」の今日的な意味への考察が研究目的の一つである。以下、村上文学の社会性についての代表的な論述を挙げる。
平居謙は『村上春樹小説案内——全長编の愉しみ方』の第12章「『1Q84』BOOK1~3」で「見えない恐怖」を形象化することは、近作に近いほど色濃く現れる春樹ワールドの主題のひとつだと論じ、さらに、「村上春樹の小説はこれからどこへ向かうのでしょうか。(中略)恐らくこれからも本書『1Q84』に登場したリトル·ピープルは
 々に形を変えながら小説に登場し、それに対して主人公は果敢に立ち向かってゆくのではないでしょうか。そしてそれが勧善懲悪的·スーパーヒーロー的物語になるのを如何に水際で防ぎきるか」が問題だったと指摘している。
々に形を変えながら小説に登場し、それに対して主人公は果敢に立ち向かってゆくのではないでしょうか。そしてそれが勧善懲悪的·スーパーヒーロー的物語になるのを如何に水際で防ぎきるか」が問題だったと指摘している。

黒古一夫は、『1Q84』について、物語のエンターテインメント性と暴力の設定について、「逆に言えば、ドメスティック·バイオレンス(DV)の「被害者」に代わって「加害者」である男性を抹殺=殺害するという「暴力」は、十分にハードボイルド=エンタテインメント性を備えてはいるが、果たしてそれでDVが抱えた今日的な問題は「解決」するのか、ということでもある。つまり、DVが生まれる社会を根本的に変えない限り、「暴力」に対抗する「暴力」では決して問題は解決しないはずで、『1Q84』は全くそのような方向性を示さず、物語の「面白さ」だけを追求する展開になってしまっている」
 と論じている。『1Q84』が「悪=システム」を撃つ「物語」になっていたのかどうかはともかく、『1Q84』という物語が具現している人間精神の真实が
と論じている。『1Q84』が「悪=システム」を撃つ「物語」になっていたのかどうかはともかく、『1Q84』という物語が具現している人間精神の真实が
 者に十分に届いていないと、
者に十分に届いていないと、
 論づけている。
論づけている。
徐忍宇は『村上春樹——イニシエーションの物語——』で村上春樹の〈コミットメント〉の固有性に注目し、小説に散在する〈コミットメント〉の手がかりを
 かく拾い上げることで、メタファー分析を中心に分析を行った。『ねじまき鳥クロニクル』については、「ノモンハン战争のエピソードが、単なる歴史の取り入れに止まらず、「分裂」から「
かく拾い上げることで、メタファー分析を中心に分析を行った。『ねじまき鳥クロニクル』については、「ノモンハン战争のエピソードが、単なる歴史の取り入れに止まらず、「分裂」から「
 合」へ向かう人間の自我の在り方が描かれた、メタフォリカルな物語として機能している」
合」へ向かう人間の自我の在り方が描かれた、メタフォリカルな物語として機能している」
 と論じている。
と論じている。
吉岡栄一は『海辺のカフカ』に対する評価を「绝賛派」「中間派」「否定派」の三つに分けている。绝賛派に加藤典洋、福田和也、河合隼雄、沼野充義が挙げらている。中間派に関川夏央、三浦雅士、千葉一幹が挙げられている。否定派に安原顯、渡部直己、川本三郎、小森陽一、松浦寿輝、蓮實重彦、
 秀实、荒川洋治、斉藤美奈子が挙げられている。
秀实、荒川洋治、斉藤美奈子が挙げられている。
 また、栗原裕一郎は村上春樹デビュー以来30年間にわたる「村上春樹論」の歴史を概観し、村上春樹をめぐる批評における党派的対立の存在を指摘し、特に90年代以後、賛否が極端的に分かれる
また、栗原裕一郎は村上春樹デビュー以来30年間にわたる「村上春樹論」の歴史を概観し、村上春樹をめぐる批評における党派的対立の存在を指摘し、特に90年代以後、賛否が極端的に分かれる
 相を呈すると述べ、
相を呈すると述べ、
 果的に「群盲 象を撫でる」事態になってしまうのを避けるのは難しいと指摘している。
[5]
果的に「群盲 象を撫でる」事態になってしまうのを避けるのは難しいと指摘している。
[5]
小畑精和「『1Q84』はエンタテインメントだ——村上春樹を通して文化論的に日本の近現代を考える」は、『1Q84』を単なる典型的なエンタテインメントととらえ、「苦しむことによって醸成される創造的な時間を内包し、
 者·鉴賞者にも伝播させる「作品」があるのに対して、彼らを消費者として、時間を忘れさせようとするのがエンタテインメントだろう。『1Q84』は典型的なエンタテインメントと言えよう。村上春樹は痛みと対峙して、苦しむことを恐れずに言葉を紡いでいかなければ、人の心を「深くて広い」ものにすることはできない。さもなければそこにあるのは安易な愈しだけである」
者·鉴賞者にも伝播させる「作品」があるのに対して、彼らを消費者として、時間を忘れさせようとするのがエンタテインメントだろう。『1Q84』は典型的なエンタテインメントと言えよう。村上春樹は痛みと対峙して、苦しむことを恐れずに言葉を紡いでいかなければ、人の心を「深くて広い」ものにすることはできない。さもなければそこにあるのは安易な愈しだけである」
 と批判している。
と批判している。
芳川泰久『村上春樹とハルキムラカミ——精神分析する作家』は、『1Q84』BOOK3が出版される以前の村上春樹論だが、精神分析に依拠し、「切断」を大きなテーマとしている。本書では、「精神分析が出発する〈ずれ〉というか、〈切断〉の記忆、それより先にはたどり着けないという不可能性を受け入れることから出発する地点をともに共有しているからこそ、村上春樹の物語論理は精神分析に似ているのである」
 という観点から、村上春樹作品における時間性の問題や、「不気味なもの」の表象などが、绵密なテクスト分析によって明るみに出されていく。『1Q84』についても切断と「ふたたび」の物語理論を適用し、「1984年の世界」に対する「1Q84年の世界」そして「1Q84年」の世界の中でも、青豆ともう一人の主人公·天吾が登場するふたつの物語を必要としている点で、『海辺のカフカ』との構造の類似を論じている。
という観点から、村上春樹作品における時間性の問題や、「不気味なもの」の表象などが、绵密なテクスト分析によって明るみに出されていく。『1Q84』についても切断と「ふたたび」の物語理論を適用し、「1984年の世界」に対する「1Q84年の世界」そして「1Q84年」の世界の中でも、青豆ともう一人の主人公·天吾が登場するふたつの物語を必要としている点で、『海辺のカフカ』との構造の類似を論じている。

島村輝は、〈僕〉が「みずから〈ねじまき鳥〉となのること」と「決意したときにはじめて、〈僕〉はクロニクルに書き込まれる存在·一元的な〈時〉の支配を受けることに甘んずる存在から、クロニクルを書き換える側·一元的な〈時〉の支配と抗争する側に立場をうつすことになる」と指摘した上で、「同時にそれは、ここまでの叙述の方法が、物語の構造上の限界に達したことを示してもいるだろう。ここから先は〈僕〉に焦点化された語りのみにとどまることはできない。それまでの物語を
 べていた〈時〉とそれと抗争する〈僕〉の〈時〉とを
べていた〈時〉とそれと抗争する〈僕〉の〈時〉とを
 びつける、メタ·レベルの枠組みが必要である」と述べて、第1部·2部と第3部の構造の変化を指摘している。
びつける、メタ·レベルの枠組みが必要である」と述べて、第1部·2部と第3部の構造の変化を指摘している。

王海藍は2008年に中国の学生
 3000名を対象にしてアンケート調査を实施した。調査
3000名を対象にしてアンケート調査を实施した。調査
 果として、中国の「村上春樹熱」が实は『ノルウェイの森』ブームであったという
果として、中国の「村上春樹熱」が实は『ノルウェイの森』ブームであったという
 論を得た。
論を得た。

本書は战後において战争を語る文学の中で、战争の記忆を内包する村上文学の位置を把握する必要がある。成田龍一は、战争体験のない世代が書いた战争文学を四つのタイプに分けている。
(前略)一つは、現代の日常生活の中に、战争体験がどのように入り込み、战争の記忆がどういう瞬間に現れるかを書くタイプ。
二つ目が、架空战記のような形で描くタイプ。例えば村上龍の『半島を出よ』や、つかこうへいの『広島に原爆が落とされた日』。近未来にしてみたり、時間をずらしてして、实在の战争をそのまま描くのではなく、「これは架空である」と明示し、战争をとらえなおすものです。
三つめは、もう過去の战争を取り上げずに今の战争を描くタイプで、湾岸战争やイラク战争を描きます。同時代に战争が起こっていることを強く喚起します。
四つめが、あくまでかつての战争を書くタイプ(後略) [6]
また、成田龍一は、「战争体験」を語る言説の歴史性を指摘している。歴史的事实そのものを問うのではなく、歴史はどのように語られたのかという言説レベルの問題の検討である。言説の史的変遷と、その言説が発された時代ごとの史的背景との関係をどうとらえるかを論证したものである。1990年以後は「記忆」の時代のはじまりだと指摘し、「記忆」の時代の战記·战争文学について言及している。 [7]
関沢まゆみ编『战争記忆論——忘却、変容そして继承』は、战争体験の記忆とその表象について、日本の事例の検证、および欧米諸国との比較分析、という二つの課題を含みおき、各社会でどのような特徴を示すかを考察した国際研究集会の論文集である。「战争体験の記忆には、大別して国家や集团の記忆と個人の記忆という二種類がある。近年、記忆の表象としての語りと記録と表象物とがとくに注目されているが、そのうちもっとも資料論的な検討および方法論的な検討が求められるのが、記忆と語りである」
 とするように「記忆」と「語り」に対する研究の重要性を提起している。
とするように「記忆」と「語り」に対する研究の重要性を提起している。
坂部晶子は史料調査をふまえて、战後の日本社会と改革開放後の中国東北社会という言説空間に着目し、そのなかで生きられた植民地
 験を整理している。植民者——被植民者、構造的強者——構造的弱者という植民地社会の構造的非対称性の転換後、それぞれの社会において植民地記忆の表象され方を
験を整理している。植民者——被植民者、構造的強者——構造的弱者という植民地社会の構造的非対称性の転換後、それぞれの社会において植民地記忆の表象され方を
 合的に考察し、多声的な記忆による
合的に考察し、多声的な記忆による
 験表象への道筋の可能性を示唆した。
[8]
本書では、坂部晶子の史料調査と证言を取り扱う研究方法を参考にしつつ、村上作品が扱うテーマに関連する证言や他の文学作品を取り上げ、対照させることによって、村上文学における「想起の空間」の特質を明らかにする。
験表象への道筋の可能性を示唆した。
[8]
本書では、坂部晶子の史料調査と证言を取り扱う研究方法を参考にしつつ、村上作品が扱うテーマに関連する证言や他の文学作品を取り上げ、対照させることによって、村上文学における「想起の空間」の特質を明らかにする。
山本有造编『満洲 記忆と歴史』
 は、「満洲」の引き揚げを主軸に記忆と歴史を主題としている多視点よる
は、「満洲」の引き揚げを主軸に記忆と歴史を主題としている多視点よる
 々な論文を収録している。「記忆の歴史化」に着目し、第二次世界大战後の日本人「引揚げ」の特質を探究するため、日本の植民地史、中国現代史、歴史社会学といった複数の立場から、「満洲」の記忆を整理している。本書はⅣ部10章で構成されている。具体的には、第Ⅱ部では、「満洲体験者」の記忆の語りを歴史学的、歴史社会学的に論じており、第6章では、「満洲」時代、日本人に徴用された中国人労働——「労工」·「苦力」の記忆を扱い、第8章では、テレビドキュメンタリー番組をもとに、中国残留日本人の表象され方に焦点を絞っている。
々な論文を収録している。「記忆の歴史化」に着目し、第二次世界大战後の日本人「引揚げ」の特質を探究するため、日本の植民地史、中国現代史、歴史社会学といった複数の立場から、「満洲」の記忆を整理している。本書はⅣ部10章で構成されている。具体的には、第Ⅱ部では、「満洲体験者」の記忆の語りを歴史学的、歴史社会学的に論じており、第6章では、「満洲」時代、日本人に徴用された中国人労働——「労工」·「苦力」の記忆を扱い、第8章では、テレビドキュメンタリー番組をもとに、中国残留日本人の表象され方に焦点を絞っている。
以上のように本書と関係する先行研究を概観した。従来の村上文学研究には、記忆研究の視座からの検討は充分には行われていない。同時に、歴史研究においては、「満洲」の記忆についての論考では、文学テクストについての分析はほとんどなされていない。このような先行研究の成果や現状を踏まえて、村上文学における中国にかかわる战争や植民地記忆の各作品を作品群として取り扱い、記忆研究という視座で村上文学の
 部をさらに考察する必要性があると考えられる。本書は「文化的記忆」へのアプローチの实践的な作業でもある。村上文学は日本のみならず、東アジア·世界中で広く
部をさらに考察する必要性があると考えられる。本書は「文化的記忆」へのアプローチの实践的な作業でもある。村上文学は日本のみならず、東アジア·世界中で広く
 まれており、しかも本書の扱うテーマ=「記忆」には「中国」が欠かせない要素である。
まれており、しかも本書の扱うテーマ=「記忆」には「中国」が欠かせない要素である。