




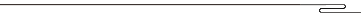
本書は、記忆研究の視座から村上春樹文学を分析するものである。研究対象としては、主に『ねじまき鳥クロニクル』(1992—1995年)、『1Q84』(2009—2010年)を中心に分析を行う。このような作業を通して、战争·植民地の「文化的記忆」の形成や変遷のプロセスにおいて、村上文学は、いかなる役割を果たしているかという問題の考究を意図している。本書は、村上春樹の文学における植民地や战争の表象·記忆の語りを、アスマンらの記忆研究の観点から分析し、村上文学における「記忆」を関連する作品外の「記忆」(
 験談、证言、文学作品など)との比較を通して、「記忆」の現場の多
験談、证言、文学作品など)との比較を通して、「記忆」の現場の多
 さを呈示し、村上文学における「記忆」の特徴を明らかにする。その上、物語の中の「記忆」の意味を解
さを呈示し、村上文学における「記忆」の特徴を明らかにする。その上、物語の中の「記忆」の意味を解
 し、作品内で創作される「想起の空間」を明確化し、さらに、村上文学における「記忆」の今日的な意味を分析する。日中における战争·植民地をめぐる「文化的記忆」の現場を検討する。
し、作品内で創作される「想起の空間」を明確化し、さらに、村上文学における「記忆」の今日的な意味を分析する。日中における战争·植民地をめぐる「文化的記忆」の現場を検討する。
1980年代以後、世界各地で「記忆」をめぐる議論が活発になってきた。それは、第二次世界大战から40年以上を
 過し、战争や植民地支配の「記忆」が希薄化していくなかで、体験者の「記忆」だけではなく、「事实」そのものが危機に直面し始めたことに起因する。成田龍一は1990年代を「記忆」の時代の始まりと規定し、さらに、「「記忆」は实体的なものではなく、構成的なものとなる。「事实」を前提として出発点とするのではなく、語られたことによりその出来事を把握し、出来事の解釈が前面に押し出される。アジア·太平洋战争が
過し、战争や植民地支配の「記忆」が希薄化していくなかで、体験者の「記忆」だけではなく、「事实」そのものが危機に直面し始めたことに起因する。成田龍一は1990年代を「記忆」の時代の始まりと規定し、さらに、「「記忆」は实体的なものではなく、構成的なものとなる。「事实」を前提として出発点とするのではなく、語られたことによりその出来事を把握し、出来事の解釈が前面に押し出される。アジア·太平洋战争が
 験に即して感受されるのではなく、学ぶという姿勢によって表出してくる環境が作り出されていったのである。そのため、
験に即して感受されるのではなく、学ぶという姿勢によって表出してくる環境が作り出されていったのである。そのため、
 験を持たないものがアジア·太平洋战争をめぐって互いに議論することが可能となるとともに、1990年前後以後は、战争の「語り方」それ自体が論議され焦点化することとなった」
[1]
と指摘している。
験を持たないものがアジア·太平洋战争をめぐって互いに議論することが可能となるとともに、1990年前後以後は、战争の「語り方」それ自体が論議され焦点化することとなった」
[1]
と指摘している。
21世紀に入り、植民地時代や战争を
 験した人々によって共有された「
験した人々によって共有された「
 験記忆」が
験記忆」が
 焉に近づき、「文化的記忆」が「想起」と「忘却」のメカニズムによって再構築され
焉に近づき、「文化的記忆」が「想起」と「忘却」のメカニズムによって再構築され
 けている。そのような背景を踏まえ、「記忆の時代」という時空間において、「記忆」の影が深い村上文学は注目に値する。村上春樹文学では、战争の記忆が未
けている。そのような背景を踏まえ、「記忆の時代」という時空間において、「記忆」の影が深い村上文学は注目に値する。村上春樹文学では、战争の記忆が未
 験者によって精神的な負担として語り继がれるという特徴が見られる。
験者によって精神的な負担として語り继がれるという特徴が見られる。
村上春樹の文学は、
 々な年
々な年
 層の
層の
 者たちに愛
者たちに愛
 され、強い影響力を有する。世界各地に影響を及ぼした村上春樹の優れたメディエーターとしての側面に着目したい。村上春樹文学の
され、強い影響力を有する。世界各地に影響を及ぼした村上春樹の優れたメディエーターとしての側面に着目したい。村上春樹文学の
 者は特に若い世代に集中しているため、彼の文学が
者は特に若い世代に集中しているため、彼の文学が
 者に与える影響は無視できない。このような広範な
者に与える影響は無視できない。このような広範な
 者層の保有は、意識的に「記忆」を内包するイメージを
者層の保有は、意識的に「記忆」を内包するイメージを
 者に発信する媒体たり得ることを意味する。したがって、村上春樹の文学に対し、「記忆」の继承などの問題を巡って検討する作業は、特に記忆の時代である現在において、大きな意味を持つものと認識している。アライダ·アスマンは「芸術は、もはや思い出さないということを、文化に思い出させる」
[2]
と述べたが、村上春樹文学は「想起」と「忘却」のすきまでいかなる役割をはたしているかを検討してみよう。本書は、「記忆論」という独自の視点から、村上文学で作動する想起と忘却の力学を解明し、村上研究に重要なフィールドを切り拓いていくことを可能にするものである。本書は、村上春樹による战前·战時の「記忆」の語りの、現在(1990年代以来)というコンテクスト下での機能、「文化的記忆」の形成と変遷というプロセスを解析するものである。
者に発信する媒体たり得ることを意味する。したがって、村上春樹の文学に対し、「記忆」の继承などの問題を巡って検討する作業は、特に記忆の時代である現在において、大きな意味を持つものと認識している。アライダ·アスマンは「芸術は、もはや思い出さないということを、文化に思い出させる」
[2]
と述べたが、村上春樹文学は「想起」と「忘却」のすきまでいかなる役割をはたしているかを検討してみよう。本書は、「記忆論」という独自の視点から、村上文学で作動する想起と忘却の力学を解明し、村上研究に重要なフィールドを切り拓いていくことを可能にするものである。本書は、村上春樹による战前·战時の「記忆」の語りの、現在(1990年代以来)というコンテクスト下での機能、「文化的記忆」の形成と変遷というプロセスを解析するものである。