




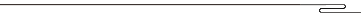
本章では『ねじまき鳥クロニクル』における「ノモンハン」と「新京の動物園」にかかわる「記忆」に焦点を当てる。すでに前章で述べたように、村上春樹の文学において、战争や植民地に関わる記忆は一つの重要な題材として多くの作品で取り扱われてきた。最初の短编「中国行きのスロウ·ボート」(1980年)をはじめ、長编『羊をめぐる冒険』(1982年)、『ねじまき鳥クロニクル』(1992—1995年)、『海辺のカフカ』(2002年)といった作品に战争の記忆は影を落としている。このような「村上春樹文学『記忆』の系譜」を引き继いで、『1Q84』ではしばしば「満洲」にまつわる記忆が語られており、「記忆」の继承という問題への意識が顕著である。これらの作品群のなかでも、特に『ねじまき鳥クロニクル』
 には対社会意識が強く示されており、「満洲国」に関わる歴史的な逸話が多く挿入されている。第1部末の「間宮中尉の長い話·1」、「間宮中尉の長い話·2」
には対社会意識が強く示されており、「満洲国」に関わる歴史的な逸話が多く挿入されている。第1部末の「間宮中尉の長い話·1」、「間宮中尉の長い話·2」
 、そして第3部の「動物園襲撃(あるいは要領の悪い虐殺)」、「ねじまき鳥クロニクル#8(あるいは二度目の要領の悪い虐殺)」
、そして第3部の「動物園襲撃(あるいは要領の悪い虐殺)」、「ねじまき鳥クロニクル#8(あるいは二度目の要領の悪い虐殺)」
 はそれぞれ「満洲国」に関わる歴史を背景としている。この点に関する先行研究は多く存在するが、「記忆」という視点からの考察は充分とはいえず、さらなる研究が必要である。
はそれぞれ「満洲国」に関わる歴史を背景としている。この点に関する先行研究は多く存在するが、「記忆」という視点からの考察は充分とはいえず、さらなる研究が必要である。
本章では、村上の文学を記忆のメディアと見なし、植民地や战争をめぐる記忆が、いかに叙述されているのか、という観点から、この作品で生産された「記忆」を明らかにする。具体的には、『ねじまき鳥クロニクル』に描かれたノモンハンの体験を、ノモンハン事件の歴史記述や、ノモンハン事件に関する記忆の他の叙述と比較し、さらには新京動植物園の歴史的な時代背景を参照しながら、分析を進めていく。本書の目的は「満洲」についての記忆を整理する作業でもないし、歴史研究でもない。本章では、植民地や战争に関する异なる
 態の「記忆」と『ねじまき鳥クロニクル』との比較を通して、村上春樹が生産した「記忆」の特徴を明らかにする。無論、テクストのなかの「記忆」の象徴的な意味を探究するためには、その「記忆」の意味を作品全体の中で解
態の「記忆」と『ねじまき鳥クロニクル』との比較を通して、村上春樹が生産した「記忆」の特徴を明らかにする。無論、テクストのなかの「記忆」の象徴的な意味を探究するためには、その「記忆」の意味を作品全体の中で解
 しなければならないが、この点については次章でさらに検討していく。
しなければならないが、この点については次章でさらに検討していく。
沼野充義は、主人公岡田トオルが住む世田谷の家の庭で鳴く鳥の鳴き声について、「この鳥は満洲の動物園の話にも登場する。だから、世田谷の日常と満州の歴史的過去をつなぐ役割をやはり果たしている」 [1] と語っている。
鈴村和成は「ただ、村上はここで、満州の歴史、日本の行った战争と現代とを歴史的に
 んでいるのかというと、必ずしもそうではない。あるいは満州の出来事でなくてもよかったかもしれない。そういう「かもしれない」という暫定性が仕組まれながら語られている歴史なんですね」
[2]
と指摘している。
んでいるのかというと、必ずしもそうではない。あるいは満州の出来事でなくてもよかったかもしれない。そういう「かもしれない」という暫定性が仕組まれながら語られている歴史なんですね」
[2]
と指摘している。
柴田勝二は、「歴史叙述自体が客観的な「出来事」の描出によって成り立つのではなく、歴史家という個的な叙述者を主体として、そこに担われた文化的文脈を偏差として含む形でしかなされない側面を持っている。(中略)『ねじまき鳥クロニクル』において、個人の暴力と国家の暴力が時空を超えて響き合う形で配され、また歴史的な事象がつねに個人をめぐる挿話として語られているのは、村上のこうした歴史認識の表現にほかならない」
 と論じている。
と論じている。