




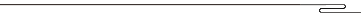
近代中国のイメージが凝縮された場所——「魔都」上海は、村上春樹文学の中でたびたび言及されている。上海の描写は分量としては多くはないが、中国を象徴するものとして取り扱われている。『風の歌を聴け』では上海の战場としてのイメージが取り扱われているのに対して、「トニー滝谷」ではモダンな植民地都市としてのイメージが描かれている。
デビュー作の中编小説『風の歌を聴け』は、最初1979年に『群像』(6月号)に掲載され、1979年7月に講談社より単行本として発行された。1985年10月には講談社より文庫版が刊行され、1990年に『村上春樹全作品1979—1989 ①』(講談社)に収録された。この作品では、語り手である「僕」の叔父が中国での战争体験を持つ設定となっている。
語り手は29才の「僕」である。「僕」は「ジェイズ·バー」で、友人の「鼠」と酒を飲み
 ける。僕は、バーの洗面所に倒れていた、左手の指が4本しかない女の子と出会い、互いに淡く親しい交わり楽しむ。こうして「僕」の毎日が淡々と過ぎて行くという物語であるが、その中で、「僕」は、三人の叔父のうちの一人が、
ける。僕は、バーの洗面所に倒れていた、左手の指が4本しかない女の子と出会い、互いに淡く親しい交わり楽しむ。こうして「僕」の毎日が淡々と過ぎて行くという物語であるが、その中で、「僕」は、三人の叔父のうちの一人が、
 战の二日後の上海で、自分で埋めた地雷を踏んで死亡したことを簡単に語る。
战の二日後の上海で、自分で埋めた地雷を踏んで死亡したことを簡単に語る。
僕には全部で三人の叔父がいたが、一人は
上海の郊外
で死んだ。
 战の二日後に自分の埋めた地雷を踏んだのだ。ただ一人生き残った三人目の叔父は手品師になって全国の温泉地を巡っている。
战の二日後に自分の埋めた地雷を踏んだのだ。ただ一人生き残った三人目の叔父は手品師になって全国の温泉地を巡っている。

「
 战の二日後に自分の埋めた地雷を踏んだ」というのは、無益な過失死なのか、自爆なのか不明であるが、少なくとも敵軍である中国軍に殺されたのではない、という設定である。第1章で、上海での叔父の战後死は唐突に
战の二日後に自分の埋めた地雷を踏んだ」というのは、無益な過失死なのか、自爆なのか不明であるが、少なくとも敵軍である中国軍に殺されたのではない、という設定である。第1章で、上海での叔父の战後死は唐突に
 者に伝えられる。「僕」は故郷の海辺の街で夏を過ごして、親友の「鼠」と旧交を温め、「小指のない女の子」という新しい恋人を得た後、試験を受けるために東京の大学へと
者に伝えられる。「僕」は故郷の海辺の街で夏を過ごして、親友の「鼠」と旧交を温め、「小指のない女の子」という新しい恋人を得た後、試験を受けるために東京の大学へと
 っていく。そして物語の
っていく。そして物語の
 末部である第38章で、「僕」は夕方、スーツ·ケースを持って、「ジェイズ·バー」にやって来て、バーテンのジェイに別れの挨拶をし、その際に叔父の战死について再び語り出す。ジェイと「僕」は、次のように語り合う。
末部である第38章で、「僕」は夕方、スーツ·ケースを持って、「ジェイズ·バー」にやって来て、バーテンのジェイに別れの挨拶をし、その際に叔父の战死について再び語り出す。ジェイと「僕」は、次のように語り合う。
「東京は楽しいかね」
「どこだって同じさ」
「だろうね。あたしは東京オリンピックの年以来一度もこの街を出たことがないんだ」
「この街は好き?」
「あんたも言ったよ。どこでも同じってさ」
「うん」
「でも何年か
 ったら一度中国に帰ってみたいね。一度も行ったことはないけどね。……港に行って船を見る渡そう思うよ」
ったら一度中国に帰ってみたいね。一度も行ったことはないけどね。……港に行って船を見る渡そう思うよ」
「僕の叔父さんは中国で死んだんだ」
「そう……。いろんな人間が死んだものね。でもみんな兄弟さ」

ここで注目したいのは、物語の舞台となっている「ジェイズ·バー」のバーテンダーであるジェイは在日中国人ということである。「僕の叔父さんは中国で死んだ」とは、第1章で绍介された、
 战の二日後に自分の埋めた地雷を踏んで死んだ叔父のことである。ジェイの答え「そう……。いろんな人間が死んだものね」からすれば、ジェイは何か言おうとしても言えなかった、という複雑な心境が現れている。ここでは、日本人と中国人がそれぞれ背負っている战争の記忆の背後に、何らかの違いがあることが暗示されている。日本の地に立って中国を眺めるジェイが感じるのは、分断された日中の距離感であろう。その距離感は短编小説「中国行きのスロウ·ボート」での「僕」の感覚と共通する。ジェイは战争を記忆し
战の二日後に自分の埋めた地雷を踏んで死んだ叔父のことである。ジェイの答え「そう……。いろんな人間が死んだものね」からすれば、ジェイは何か言おうとしても言えなかった、という複雑な心境が現れている。ここでは、日本人と中国人がそれぞれ背負っている战争の記忆の背後に、何らかの違いがあることが暗示されている。日本の地に立って中国を眺めるジェイが感じるのは、分断された日中の距離感であろう。その距離感は短编小説「中国行きのスロウ·ボート」での「僕」の感覚と共通する。ジェイは战争を記忆し
 けようとする青年たちを、彼らの隣で見守る人生
けようとする青年たちを、彼らの隣で見守る人生
 験の豊かな叔父のような人物でもあるのだ。藤井省三は「ジェイズ·バー」について次のように述べている。「ジェイズ·バー」とは、日中战争、朝鮮战争、及びベトナム战争という、二十世紀の半ばに東アジアで日中米の三ヵ国が関係した战争体験を想起する場だとも言える。
験の豊かな叔父のような人物でもあるのだ。藤井省三は「ジェイズ·バー」について次のように述べている。「ジェイズ·バー」とは、日中战争、朝鮮战争、及びベトナム战争という、二十世紀の半ばに東アジアで日中米の三ヵ国が関係した战争体験を想起する場だとも言える。
 そして、在日中国人ジェイは、アメリカ占領軍の兵士により英語名を命名されて中国名を失ったのである。
そして、在日中国人ジェイは、アメリカ占領軍の兵士により英語名を命名されて中国名を失ったのである。

中国と関わる記忆が暗示される箇所はもう一つある。「僕」は「ジェイズ·バー」を出て、東京行きの夜行バスの待合所のベンチに座り、遠い汽笛が運んでくる微かな海風に包まれて、消えてゆく街の灯を眺める。「僕」の乗車の場面は注目に値する。
バスの入口には二人の乗務員が両脇に立って切符と座席番号をチェックしてた。僕が切符を渡すと、彼は「21番のチャイナ」と言った。
「チャイナ?」
「そう、21番のC席、頭文字ですよ。Aはアメリカ、Bはブラジル、Cはチャイナ、Dはデンマーク。こいつが聞き違えると困るんでね」
彼はそう言って座席表をチェックしている相棒を指さした。

乗務員が聞き間違えを防ぐために、Cをチャイナと
 み上げる。これはさきほどジェイとの会話で言及されていた、中国と関わる战争の記忆を示唆している。「僕」は「21番のチャイナ」という言い方を聴いて、錯覚したように「チャイナ?」と戸惑う。それは自己にとっての他者=「中国」、或いは他者としての「中国」を内面化する自己に対して、懐疑的な状態に陥っていることを表している。
み上げる。これはさきほどジェイとの会話で言及されていた、中国と関わる战争の記忆を示唆している。「僕」は「21番のチャイナ」という言い方を聴いて、錯覚したように「チャイナ?」と戸惑う。それは自己にとっての他者=「中国」、或いは他者としての「中国」を内面化する自己に対して、懐疑的な状態に陥っていることを表している。
こうした中国に関わる战争の記忆は、「中国行きのスロウ·ボート」第1章末の「死はなぜかしら僕に、中国人のことを思い出させる」
 という一文にも暗示されている。中国に関わる「記忆」は、村上の初期の作品からすでに影を落としているのである。
という一文にも暗示されている。中国に関わる「記忆」は、村上の初期の作品からすでに影を落としているのである。
「トニー滝谷」は、最初『文藝春秋』の1990年6月号に掲載された短编小説である。この版をショートバージョンとすると、1991年の『村上春樹全作品1979—1989 ⑧ 短编集Ⅲ』(講談社)、1999年の『レキシントンの幽霊』(文藝春秋)に収録された版は、大幅に加筆されたロングバージョンとなっている。また、「トニー滝谷」は2005年に市川準監督により、イッセー尾形主演で映画化され、第57回ロカルノ国際映画祭(スイス)コンペ部門審査員特別賞などを受賞した。
主人公であるトニー滝谷は日本人でありながら、混血児のような名前を付けられた。彼の父親である滝谷省三郎は1937年に中国の上海を訪れ、ジャズトロンボーン奏者として働いていた。孤独を抱えて成長したトニー滝谷は、イラストレーターとして才能を発揮し、その道で成功を収める。着こなしの美しい娘に恋をし、
 婚するが、妻の度を越した衣服に対する執着は、彼女を死に追いやってしまう。トニーは亡き妻の大量の衣服を着てくれる女性を雇おうとするが、やがて部屋いっぱいの衣服は妻の存在の影に過ぎないことを感じ、女性を断り、妻の衣服をすべて売り払う。父の死後、その遺品である膨大なレコード·コレクションが彼自身を息苦しくさせていたのでそれを売り払う。その後、彼は自分が本当に孤独になったと自覚した。
婚するが、妻の度を越した衣服に対する執着は、彼女を死に追いやってしまう。トニーは亡き妻の大量の衣服を着てくれる女性を雇おうとするが、やがて部屋いっぱいの衣服は妻の存在の影に過ぎないことを感じ、女性を断り、妻の衣服をすべて売り払う。父の死後、その遺品である膨大なレコード·コレクションが彼自身を息苦しくさせていたのでそれを売り払う。その後、彼は自分が本当に孤独になったと自覚した。
藤井省三は、「トニー滝谷」のそれぞれ异なるバージョンと『ねじまき鳥クロニクル』、「ねじまき鳥クロニクルと火曜日の女たち」(『新潮』1986年1月号)との比較を通して、「初出
 版『ねじまき鳥 第1部』では歴史に対する永遠の傍観者である孤独なトニー滝谷を登場させることにより、主人公の「僕」すなわちオカダトオルに日本の現代史への参与を促した」
版『ねじまき鳥 第1部』では歴史に対する永遠の傍観者である孤独なトニー滝谷を登場させることにより、主人公の「僕」すなわちオカダトオルに日本の現代史への参与を促した」
 と論じている。初出のショートバージョンとその後のロングバーションでは、上記の粗筋には変化はないが、藤井省三は、以下の部分に大きな違いがあると論じている。ここで対比して分析する。
と論じている。初出のショートバージョンとその後のロングバーションでは、上記の粗筋には変化はないが、藤井省三は、以下の部分に大きな違いがあると論じている。ここで対比して分析する。
【ショートバージョン】
彼の父親は滝谷省三郎という、战前から少しは名を知られたジャズ·トロンボーン吹きだった。しかし
战争の始まる三年前に
、ちょっとした面倒を起こして東京を離れなくてはならなくなり、どうぜ離れるならということで中国にわたった。そして、日中战争から真珠湾攻撃、そして原爆投下へと到る战乱激動の時代を、
上海や大連
のナイトクラブで気楽にトロンボーンを吹いて過ごした。

【ロングバージョン】
彼の父親は滝谷省三郎という、战前から少しは名を知られたジャズ·トロンボーン吹きだった。しかし
太平洋战争の始まる四年ばかり前に
、女の
 んだ面倒を起こして東京を離れなくてはならなくなり、どうせ離れるならということで楽器ひとつを持って中国にわたった。その当時、長崎から一日船に乗れば上海に着いた。彼は東京にも日本にも、失って困るようなものを一切持ちあわせなかった。だから未練の持ちようもなかった。それにどちらかといえばその当時の上海という街が提供する技巧的なあでやかさの方が彼の性格にはよくあっていたようだった。
揚子江を
んだ面倒を起こして東京を離れなくてはならなくなり、どうせ離れるならということで楽器ひとつを持って中国にわたった。その当時、長崎から一日船に乗れば上海に着いた。彼は東京にも日本にも、失って困るようなものを一切持ちあわせなかった。だから未練の持ちようもなかった。それにどちらかといえばその当時の上海という街が提供する技巧的なあでやかさの方が彼の性格にはよくあっていたようだった。
揚子江を
 る船のデッキに立ち朝の光に輝く上海の優美
な街並を目にしたときから、滝谷省三郎はこの街がすっかり気に入ってしまっ
た。その光は彼にひどく明るい何かを
る船のデッキに立ち朝の光に輝く上海の優美
な街並を目にしたときから、滝谷省三郎はこの街がすっかり気に入ってしまっ
た。その光は彼にひどく明るい何かを
 束しているように見えた。
彼はそのとき二十一歳だった。
束しているように見えた。
彼はそのとき二十一歳だった。
そのようなわけで、日中战争から真珠湾攻撃、そして原爆投下へと到る战乱激動の時代を、彼は上海のナイトクラブで気楽にトロンボーンを吹いて過ごした。战争は彼とはまったく関係のないところで行われていた。要するに、 滝谷省三郎は歴史に対する意志とか省察とかいったようなものをまったくといっていいほど持ちあわせない人間だったのだ 。好きにトロンボーンが吹けて、まずまずの食事が一日に三度食べられて、女が何人かまわりにいれば、それ以上はとくに何も望まなかった。
彼は謙虚であり、同時に傲慢な男だった。

まず、時間の設定に変化が見える。省三郎の上海渡航時期は「战争の始まる三年前」から、「太平洋战争の始まる四年ばかり前」へと遅らされた。ロングバージョンでは、上海という都市の街並みの描写が付け加えられた。植民地下の上海の退廃的なイメージと滝谷省三郎の人物像が見事に溶け込み合っている。また、トニーの父親である省三郎に関する記述が興味深い。「歴史に対する意志とか省察とかいったようなものをまったくといっていいほど持ちあわせない人間」という語り手の叙述からは、作者村上のスタンスが垣間見えるだろう。日中战争と上海体験は、トニーの父親である省三郎にとって「関係のない」ように見える。しかし、歴史的实相を見ると、「太平洋战争の始まる四年前」、即ち1941年より4年前の1937年とは、盧溝橋事件とともに日中战争が全面的に始まった年である。同年8月13日に、日本軍は上海に侵攻し、人々は战争の波に巻きこまれていった。このような战時下の上海での記忆は「ナイトクラブで気楽にトロンボーンを吹いて過ごした」という形で語られており、記忆の空白が生じていることが暗示されている。省三郎が時代の激流の中で孤独で虚無的な人生を送ったのに対して、子世代のトニー滝谷は妻を失い、まるで父親の人生を反復するように孤独で永遠の傍観者となる。
この作品においては、世代間における「記忆」の引き继ぎというテーマは前面化されていないが、トニー滝谷が『ねじまき鳥クロニクル』にも登場することから見れば、短编「トニー滝谷」をある程度まで『ねじまき鳥』への予備段階と見なすことも可能である。 [2] 世代間における「記忆」の引き继ぎというテーマは、後の『1Q84』でも追求されていく。