




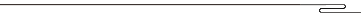
村上春樹文学には战争や植民地に関わる記忆が重い影として生息している。アジア、特に中国に関わる記忆は、多くの作品に潜在的に表現されたり、あるいは前面に押し出されたりしている。デビュー作の『風の歌を聴け』(1979年)と最初の短编「中国行きのスロウ·ボート」(1980年)から、長编『羊をめぐる冒険』(1982年)、短编「トニー滝谷」(1990年)、長编『ねじまき鳥クロニクル』(1992—1995年)、紀行文「ノモンハン鉄の墓場」(1998年)、そして『海辺のカフカ』(2002年)、『アフターダーク』(2004年)に至る作品に、战争や植民地に関わる記忆は影を落としている。これらの作品では、中国人に視
 を向けたり、あるいは物語の舞台がかつての中国となっていたりする。村上にとって中国は「書こうと思って苦心して想像するものではなく」、「人生おける重要な「記号」」
[1]
であり、自己の中に内在する他者でもある。その中国を内包する記忆を語る、いわば「村上春樹文学の伝
を向けたり、あるいは物語の舞台がかつての中国となっていたりする。村上にとって中国は「書こうと思って苦心して想像するものではなく」、「人生おける重要な「記号」」
[1]
であり、自己の中に内在する他者でもある。その中国を内包する記忆を語る、いわば「村上春樹文学の伝
 」を引き继いで、『1Q84』(2009—2010年)では、しばしば「満蒙開拓」にまつわる個人の記忆が挿入され、とりわけ、親子関係にかかわる「記忆」の继承という問題への意識が明らかに見える。藤井省三は『村上春樹のなかの中国』で、「歴史の記忆の影とは、父の战争体験を继承することにより村上の内面でも形成されたある種のトラウマと言っても過言ではあるまい」
」を引き继いで、『1Q84』(2009—2010年)では、しばしば「満蒙開拓」にまつわる個人の記忆が挿入され、とりわけ、親子関係にかかわる「記忆」の继承という問題への意識が明らかに見える。藤井省三は『村上春樹のなかの中国』で、「歴史の記忆の影とは、父の战争体験を继承することにより村上の内面でも形成されたある種のトラウマと言っても過言ではあるまい」
 と指摘している。本章では、村上の諸作品中から、「記忆」の表象を析出し、村上文学における「想起の空間」を概観し、さらなる検討の可能性を呈示する。
と指摘している。本章では、村上の諸作品中から、「記忆」の表象を析出し、村上文学における「想起の空間」を概観し、さらなる検討の可能性を呈示する。